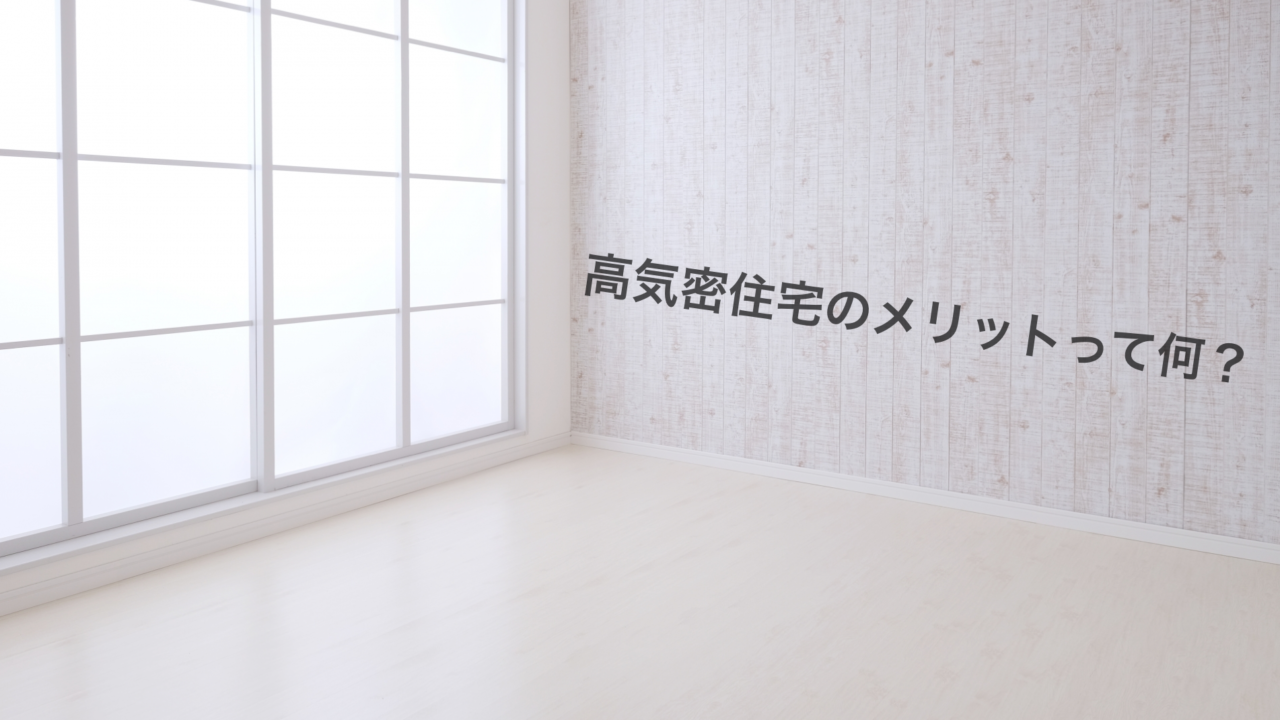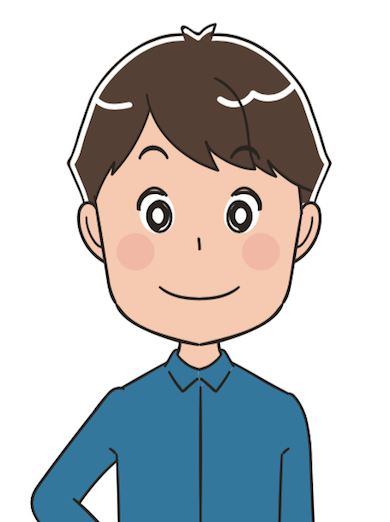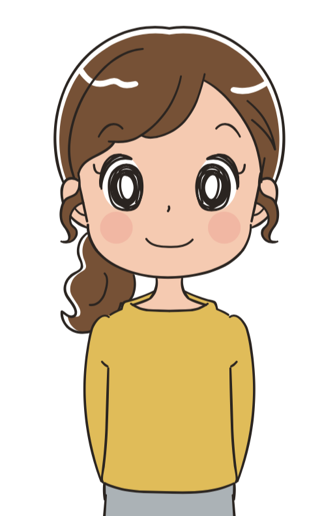元住宅営業マンで、現在は「どのハウスメーカーにも属さない立場」から、お家づくりに必要不可欠なお役立ち情報を提供しております。
当サイトにお越しいただいた方々には、ぜひ「マイホーム計画に活かせる知識」をお持ち帰りいただきたいと思っております。
今回は、「高気密住宅」に関する情報をお届けしたいと思っております。
「家の快適性」について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にして見てください。
元住宅営業マンも納得の満足度
 外出不要!自宅で効率的な家づくりが可能。
外出不要!自宅で効率的な家づくりが可能。- 作成した間取りの数は、契約前プランのこだわりとアイデアの量に比例する!
- 見比べた見積書の数は、契約前の値引き交渉の知恵と材料の多さに比例する!
無料で間取り・見積書を取り寄せられるwebサービスを上手く活用し、理想のマイホームを必ず実現させましょう。
※まずは無料請求の手順と資料サンプルを確認したい方はこちらの記事でご紹介しております。
高気密住宅は「快適な住まい」の実現に必要不可欠
「今のアパートでは冬場、暖房をかけてもかけても暖かくならない…!」
「廊下に出た途端、急激に寒さを感じる…」
今のお住いの環境の中で、このような悩みを抱えられている方々も多いのではないでしょうか?
日本には「猛暑の夏」があれば「極寒の冬」もありますので、私も含め、年中気温や気候に左右されながら生きていかなければなりませんよね…
夏場であれば、特にアパートの2階に住まわれている方は「ものすごく暑い室内環境」になりがちではないですか?
また、冬場であれば、特にアパートの1階に住まわれている方は「底冷えの激しい室内環境」になりがちではないでしょうか?(私は毎年足元の冷えから「しもやけ」を経験しておりました…)
今まさにマイホーム計画を立てられている方々にとって、新築の室内環境の快適性能は「ハウスメーカー選びの一つの基準」とも言える重要な関心ポイントだと思います。
そして、その「室内の快適性」には、家の「断熱性」「気密性」「換気システム」の効率的な相互作用が必要不可欠です。
そこで今回は、「気密性」に焦点を当てながら、高気密住宅と快適性を見ていきたいと思います。
▼合わせて読みたい記事▼
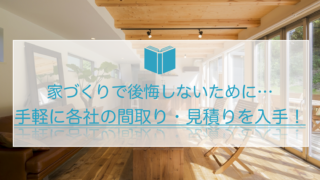
高気密住宅の「気密性」ってそもそも何?
高気密住宅は、名前の通り「気密性能の高い住宅」であることは、皆さんもなんとなくお分かりですよね?
では、気密性能が高い住宅って、そもそもどんな住宅なのでしょうか?
先に答えを言ってしまうと、気密性能が高い住宅は、
「施行によって生じる「建物の隙間」が少なく、エネルギーロスが少ない、かつ効率的な換気計画を実行できる住宅」
であることが考えられます。
建物の隙間が少なければ少ないほど、
- 隙間から室内の空気が逃げない住宅
- 隙間から外気が入り込まない住宅
- 効率よく空気循環を行うことができる住宅
というようなポジティブな要因を含むことができ、後にもご説明させていただきますが、その要因はそのまま「室内の快適性の向上」へとつながっていきます。
気密性C値
建物に隙間がどれだけあるのかは、「C値」と呼ばれる数値で表示することができます。
C値は「相当隙間面積」を表す単位で、「建物の床面積1㎡当たりの隙間面積(㎠)」を指しておりますね。
例えば、延べ床面積が132㎡の住宅に660㎠の隙間が空いていた場合、C値は5.0になります。
逆に言えば、C値が5.0の場合であれば、その家の総隙間面積は「A4サイズの紙1枚分」の隙間が空いていることになります。
また、同じく延べ床面積が132㎡の住宅に、今度は264㎠の隙間が空いていた場合、C値は2.0になります。
逆に言えば、C値が2.0の場合であれば、その家の総隙間面積は「ハガキ2枚分」の隙間しか空いていることになりますね。
●C値=相当隙間面積(家の隙間合計(㎠)÷延べ床面積(㎡))●
| C値 | 延べ床面積 | 家の総隙間面積 | 例え |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 40坪(132㎡) | 660㎠ | A4紙(ハガキ4枚半) |
| 2.0 | 40坪(132㎡) | 264㎠ | ハガキ約2枚 |
つまり、このC値が低ければ低いほど、家の隙間は少なく「高気密住宅」と呼ぶことができます。
このように感じた方も多いかと思いますので、ぜひ「そのハウスメーカーの気密性ってどうなんだろう?」と感じられた方々は、C値で質問してみるようにしてください。
(ハウスメーカーの中にはC値を公表していない会社も多いのですが、それでは快適性に全幅の信頼を寄せることができません。気密性能に関しては要確認ですね。)
気密性C値の算出はどうやってるの…?
気密性を算出するためには「気密測定」を行うことが必要不可欠です。
気密測定の概要は、
- 建物内の空気を「排出専用のファン」によって送風
- 減圧状態の室内に、建物の隙間から外気が侵入してくる
- 建物内部と外部の圧力差を何箇所か測定し、その風量をグラフ化する
- 9.8Pa時の通気量から建物の隙間面積を算出
というような流れになります。
●参考画像●

このような、
- 送風機とコントローラー
- 風量計
- 温度計
- 圧力計
などの専用機器を使うことで、気密測定を実行し、その建物のC値を算出することができるのです。
補足ですが、当然
- C値を測定するタイミングは「住める状態まで完成した建物」
で測定しなければ、快適性を考える上での指標として使うことができません。
なので、
- C値は工場内で測定した実験データのものを表示
- 建物が完成する前の「箱」の状態のタイミングでの測定
- 気密テープを貼りまくった「住む環境とは明らかに異なる状態」での測定
であれば、気密測定をする意味は全くありません。(ハウスメーカーのアピールに過ぎないです。)
なので、高気密住宅を考えていくにあたっては、
- いつ気密測定を行なっているのか
- どのような状態で行なっているのか
- 公表されている気密値は「各邸ごとに測定」した上での最低保証値なのか、それとも平均値なのか
に関しては、必ず確認するようにしてください。
(この内容は、一条工務店の評判・口コミを紹介した記事でもご紹介しております。)
高気密住宅のメリット
それでは次に、高気密住宅のメリットについて見ていきたいと思います。
高気密住宅のメリットは、大きくまとめると以下の9点です。
●高気密住宅のメリット●
- 高気密住宅であれば、外の冷気・暖気が室内に侵入しにくい
- 高気密住宅であれば、外の汚れた空気が室内に侵入しにくい
- 高気密住宅であれば、室内の温度が逃げにくい
- 高気密住宅であれば、壁内結露を抑制できる
- 高気密住宅であれば、効率的な換気計画を実行できる
- 高気密住宅であれば、部屋間の温度差を軽減できる
- 高気密住宅であれば、1階と2階の温度差を軽減できる
- 高気密住宅であれば、年中通じて平均的な湿度をコントロールしやすい
- 高気密住宅であれば、光熱費削減が容易
高気密住宅のメリット①…外の冷気・暖気が室内に侵入しにくい
まず、高気密住宅のメリットとしては、
- 夏場であれば「外の暑い空気」が室内に侵入しにくい
- 冬場であれば「外の冷たい空気」が室内に侵入しにくい
ということが挙げられます。
例えば、先ほどの「C値の数値計算例」で出した家の状況で考えた時に、
- C値=5.0であればハガキ4枚半
- C値=2.0であればハガキ2枚弱
の隙間が空いていることになります。
同じ大きさの建物であっても、相手いる隙間の面積が倍以上違ってきますので、当然C値=2.0の住宅の方が「外からの温度の侵入」を防ぐことができますよね。
言い換えると、
- 夏場であれば、空気が逃げていくため「冷房が効きにくい」
- 冬場であれば、空気が逃げていくため「暖房が効きにくい」
と言えます。
室内温度を長時間持続させられる住まい環境を、高気密住宅であれば実現させられる可能性が高まります。
高気密住宅のメリット②…外の汚れた空気が室内に侵入しにくい
また、外気の侵入に関してもう一つ気にしておかなければいけない内容が、
- 外気の空気は室内の空気よりも汚れている
ということです。
もともと古来の住まい環境においては、
- 風を循環させることで室内換気を行なっていた
という歴史があります。
つまり、気密もへったくれもなかったのです。
しかし、ここ最近で急激に高気密住宅の必要性が叫ばれているのは、外気の汚れがひどくなってきたことが原因の一つに挙げられます。
- 工場の排気ガス
- 車や乗り物の排気ガス
- PM2.5
- etc…
今では、「室内の空気の方が外気の空気よりも綺麗」になってしまったんですね。
なので、隙間が大きければ大きいほど、外部の汚れた空気の侵入を許してしまうので、結果的にどれだけ性能のいい空気清浄機や換気システムを導入しても意味がありません。
外の不純物を室内に侵入させないことは、高気密住宅のメリットだと考えられます。
高気密住宅のメリット③…室内の温度が逃げにくい
先ほどとは逆に、
- 夏場であれば、一度冷やした室内温度が外に逃げていきにくい
- 冬場であれば、一度温めた室内温度が外に逃げていきにくい
住環境を実現できることが、高気密住宅のメリットとして考えられます。
言い換えれば、
- 一度冷やした室内温度が外に逃げていきにくい
- 一度温めた室内温度が冷えにくい
というような「保温機能」のメリットがあると考えられますね。
一度室内の温度を冷ましたり、または温めてしまうことで、その温度を長時間保つことができれば、エアコンを乱用する必要もなくなり、必然的に光熱費カットにもつながります。(「高気密住宅のメリット⑨…光熱費削減が容易」の内容と関連。)
高気密住宅のメリット④…壁内結露を抑制できる
隙間が多い住宅において、その隙間を行き来しているのは温度だけではありません。
- 空気中の湿度も隙間を行き来している
ということを忘れないでください。
昔の住宅であれば、自然の風を通通に行き交わせることで室内換気をしておりましたが、現在の住宅は「家の密閉」を重視した「換気システム導入を義務付けられた住環境」づくりが求められます。
室内の湿度が建物の隙間を通過して行き着く先は構造体内であり、つまりは「壁内」なのですね。
こちらの記事の「グラスウールは最高の断熱材?元住宅営業マンが伝えたい真実」でもご紹介させていただきましたが、壁内結露は最悪の場合「腐朽菌を発生させた後に、住まいの病気を引き起こす」ことにつながります。
高気密住宅は、住まいの病気の根源を断つことからも、家の快適性の大きなメリットになっているのですね。
高気密住宅のメリット⑤…効率的な換気計画を実行できる
高気密住宅の最も大きなメリットかもしれませんが、
- 高気密住宅であれば「効率的な換気を24時間行うことができる」
点が魅力です。
現在の住宅においては、
- 機械で室内の湿度・温度を強制的に循環させる
- 機械で室内の汚れた空気を排出する
ことが多くなってきました。
ハウスメーカーでは、ほとんどの会社が「換気システム」あるいは「暖冷房機能付きの換気システム」を導入しておりますね。
一方で、たとえどれだけ性能の良い換気システムを動かしても、
- 隙間が多ければ多いほど、空気の循環が悪くなってしまう
- 隙間が多ければ多いほど、温度と湿度の室内調整ができなくなる
- 隙間が多ければ多いほど、強制的に室内の汚れてきた空気を排出できなくなる
というように、気密性能の低さによってネガティブ要因が生まれてしまいます。
逆に言えば、
「高気密住宅であればあるほど、隙間から空気が逃げていく率が減少するため、効果的な空気の循環が期待できる」
と言えるのですね。
快適な住まいに欠かせない換気システムは、高気密住宅であるからこそ効果を発揮するということを覚えておいてくださいね。
なので、ハウスメーカーを見学する際は、基本的には「気密性と換気システム」をセットで確認するようにしてください。
高気密住宅のメリット⑥…部屋間の温度差を軽減できる
先ほどの高気密住宅のメリットと関連している内容で、
「部屋間の温度さを少なくさせることができる」
点も、住まいの快適性を考える上では非常に大きなメリットです。
冬場の環境で例えてみますと、今のお住いの中で、
「リビングはよくいる空間だから30度近くまで温めている」
というご家庭の方でも、お風呂に入ろうと廊下へ出たり、浴室に行った時に
「さむ!」
「冷たっ!」
というような、空間ごとに激しい温度差を感じた経験のある方も多いかと思います。
実はこの現象、目には見えていないのですが、
- 急激な身体の温度変化
- 足裏からの、体の急激な冷え
などが原因で、人体の健康に悪い影響を与えております。
特に、お年寄りのや心臓の弱い方にとっては、体に大きな負担を感じることになり、最悪の場合は心肺停止の引き金にもなり得ます。
これがヒートショックです。
そのヒートショック等の「健康への被害」を生むきっかけとなる「部屋間の温度差」を、高気密住宅であれば軽減させることができます。
高気密住宅のメリット⑦…1階と2階の温度差を軽減できる
上記にメリットの「上下」バージョンです。
先ほどは「冬場を想定」した考え方でしたが、「夏場を想定」した場合、二階部分は非常に熱がこもりやすいため、暑いです。
しかし、高気密住宅なら、上下の温度差も「効率よく空気を循環」させることで軽減させられます。
なので、夏場であっても冬場であっても、高気密住宅では住み心地の良い住まい空間を維持することができるのですね。
高気密住宅のメリット⑧…年中通じて平均的な湿度をコントロールしやすい
特に冬場に関しては、部屋中が乾燥してしまうことが考えられますが、こちらに関しても
「高い気密性の住宅であれば、換気システムの湿度調整効果が高まるため、潤った空気を保つことができる」
というようなメリットが期待でいます。
「乾燥状態」は、あらゆる病原菌の好む空間です。
健康を考えた時、室内環境を「病原菌の住み着きにくい空間」にしてしまうことで、風邪やウイルスへの抜本的な予防対策にもなり得ます。
高気密住宅のメリット⑨…光熱費削減が容易
最後に「光熱費の削減」の観点から考えた時、高気密住宅には大きなメリットが感じられるでしょう。
今までご紹介させていただいた上記のメリットの内容から、
- 高気密住宅であれば室内の温度を一定に保ちやすい
- ある程度室内温度を快適な状態にすれば、その後は温度を維持しやすい
- 換気システム自体が効率よく作動するため、温度や湿度を調節しやすい
というようなポジティブ要因を得られる住宅であることが考えられます。
言い換えれば、
「むやみやたらにエアコンを運動させたり、空気清浄機や加湿器を使用したりする必要がなくなる」
と考えることができるため、必然的に光熱費が下がるのです。
まとめ…高気密住宅を実現させ、理想のマイホームを…
※「資料請求、どうしようかな…」と迷っている方は、先に資料請求の手順・郵送方法を確認してみましょう。
元住宅営業マンも納得の満足度

- 作成した間取りの数は、契約プランの「こだわりとアイデアの量」に比例する!
- 見比べた見積書の数は、値引き交渉の「知恵と材料の多さ」に比例する!
無料で間取り・見積書を取り寄せられるwebサービスを上手く活用し、理想のマイホームを必ず実現させましょう。
※まずは無料請求の手順と資料サンプルを確認したい方はこちらの記事でご紹介しております。
【PR】タウンライフ家づくり